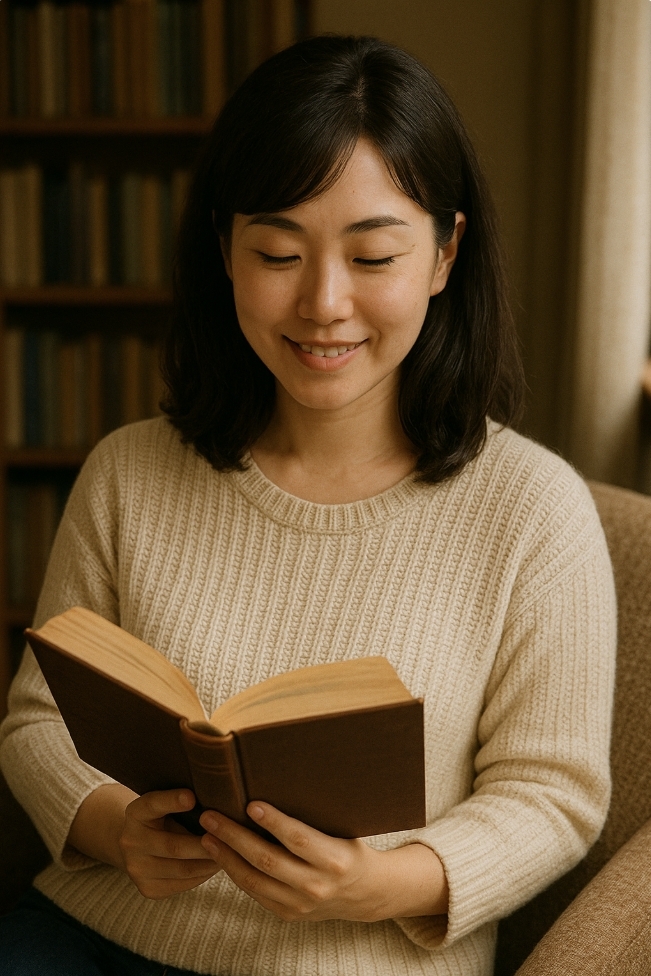2025年8月7日【読書の効能を最大限にする】方法
今日は面談の予定の他、週末のイベントに向けて、その資料などの準備を進めているところです。 これからの時間も、もう少しその準備に勤しむことになりそうですが、 しっかりと準備を重ねていきたいと思っています。 さて、本日の本題です。
読書は“智慧との出合い”である
以前の記事の中で「経営者として書籍や芸術に触れることは大変有意義である」というお話をさせていただきましたが、
<2025年7月22日開業8周年を迎えました!【時間とお金の真の意義】>
https://muratax.com/2025/07/22/9206/
今日はその中でも「読書」について、私なりの考えを書かせていただければと思います。
全てを読まない前提で臨む読書
読書というものは、その道の先輩や、人生で出会うことのないような人物の智慧を、極めて安価で得られるもの。 したがって、その使い方次第で、自分の価値観や考え方に大きな影響を与える存在になることもあるでしょう。 ただ、そうは言っても書籍の数は膨大で、すべてに目を通すことは現実的ではありません。 その前提を踏まえると、「すべて読まないことを前提にする」という考え方もアリなのではないでしょうか。 本の構成というのは、起承転結やPREP法などで、 重要な部分とそうでない部分が織り交ぜられているのが一般的です。 <参考記事:PREP法とは?-ChatworkHPより> であれば、その「重要なエッセンス」にだけ集中して、 短時間で読み取りに行くというスタイルも考えられるのではないかというところ。
「部分読み」が有効なジャンルとは?
こういった読み方は、特にビジネス書に有効だと私は考えています。 芸術や小説のような分野では、その文脈の移り変わりが重要になるため、ポイントだけ読むという読み方には向かないかもしれません。 そういう意味では、ビジネス書に限っていえば 「全体の2~3割を読めば十分」というケースもあるように、私は思っています。
学びがなければ“損切り”も必要
ただ、それでも「自分にとってはあまり学びがなかったな…」という本に出合うことはあります。 むしろ、そういった本の方が多い位かもしれません(汗)。 そんな時に大切なのが、「損切り」です。 お金を出して購入したからといって、最後まで読み切ろうとすると、時間を無駄にしてしまうことも多々あります。 本に費やした金額以上に、そこに使う時間がもったいない… そう考えた際、経営者としては思い切って損切りをし、 その分の時間をより価値ある読書や仕事に回すべきではないでしょうか。
小説・古典は“つながり”を育てる読書
一方で、小説や文学、古典などの分野は少し違います。 これらは抽象的な表現が多く、そこから自分の経営に具体的に落とし込むことができることもあるというもの。 そのような分野の読書を通して、異なる分野の本の内容が有機的につながっていくこともあるように感じます。 また、そのつながりが、結果的に自分が持っている軸をさらに強化することにも繋がるのかなというところ。
自分なりの読書スタイルを持とう
いろいろ述べては来ましたが、 様々な視点から見て、読書は非常に有意義なものであると言えます。 だからこそ、ぜひ自分なりの読書スタイルを見直して、 経営においてのヒントを掴んでいく動きをしてみてはいかがでしょうか。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・読書とは、著者の智慧を破格で獲得できる貴重な営みであると言える。 ・すべての本を読む必要はなく、大切なのはエッセンスの抽出である。 ・小説や古典など、普段触れない分野にも目を向け、経営におけるヒントを掴みにいくことを心がけたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。