2025年10月7日損益の把握に加えて「資金増減」の把握も
昨日の冒頭でも書かせていただきましたが、今週は面談がかなり立て続いている週となります。
先ほど本日の面談を終えたところなのですが、どうも熱っぽい感じがして、体調を崩したかもしれないという感覚です。
ただ、そんなことはきっと気のせいですので(!)、しっかりと気持ちを前向きに取り組んでいきたいと思います。
さて、本日の本題です。
3ヶ月に一度の面談で見える「経営の傾向」
弊所においては、基本的に3ヶ月に一度のご面談で、損益の推移や前期比較などをお話しさせていただいています。
この前年との比較や月次損益の推移を見ることで経営の傾向が明確になり、特に前期との変化を共有することで、数字から新たな気づきを得ることが多いものです。
(この話をするのが、私自身結構好きな時間だったりもします。)
「儲かっている感覚」と実際のズレ
それとともに、儲かっている感覚と実際の数値が違うということも往々にしてあります。
その大きな原因の一つが、資金繰りと損益の把握の仕方が違うということなんですね。
損益計算書は収益と経費を会計上で計上したものですが、資金繰りはあくまで現金の動きをベースにしています。
この違いこそが、感覚のズレを生む要因なんですね。
減価償却費と借入金返済
代表的な要因のひとつが「減価償却費」です。
減価償却費は、過去に支出が終わっているものを会計上で少しずつ経費化していく仕組みですので、経費として計上されていても、実際の現金の支出はありません。
もうひとつ大きいのが借入金の返済です。
借入金は入金時に収入として損益には計上されないことと同じく、返済時も同様に経費にはなりません。
つまり、会計上は経費に含まれないにも関わらず、実際には現金が出ていくという形になるため、損益よりも実際の支出が多くなる構造なんですね。
こうした点を踏まえると、損益の数字だけを見るのではなく、減価償却費や借入金の返済を加味したうえで、それをペイできる売上高を意識することが大切です。
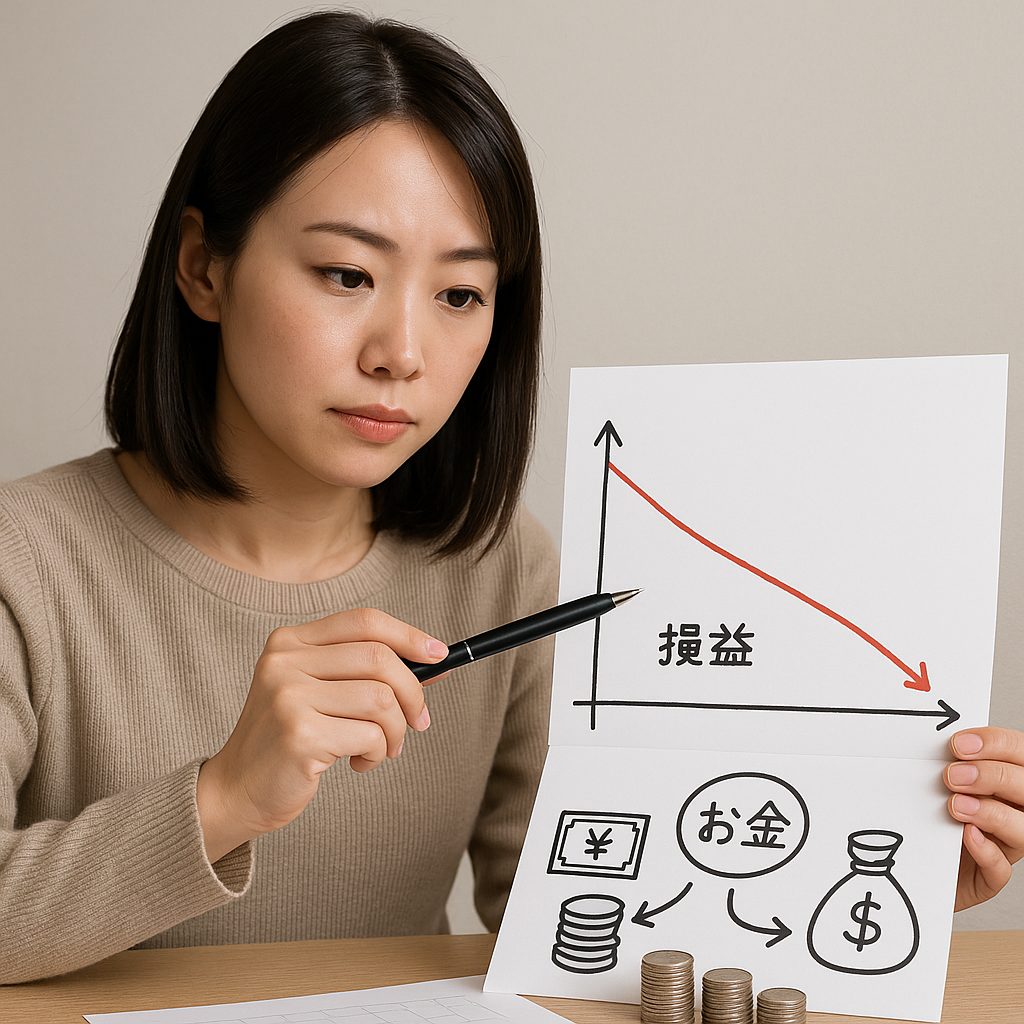
消費税の納税積立も意識する
また、忘れてはいけないのが消費税の納税積立です。
消費税は往々にして利益の多寡に関わらず発生する税金ですので、あらかじめ積立をしておかないと、納税時に資金繰りを圧迫することになりかねません。
売掛金・買掛金・在庫の影響
さらに、売掛金・買掛金といった現金の動きを伴わない項目も、資金繰りに大きく影響します。
特に在庫を抱えるビジネスでは、在庫そのものが現金化されていない支出となり、キャッシュフローを悪化させる要因になりがちです。
損益だけでなく「現金の流れ」を見るべし
どうしても損益計算書上の利益だけで経営状況を判断しがちですが、真に重要なのは「経営の血液とも言える現金の流れ」です。
損益と資金繰り、両方の視点から自社の財務を捉えることで、より安定した経営判断が可能になりますので、
そのようなことを念頭に置き、的確に自社の状況を把握することを心がけたいものですね。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・損益の数字と実際の儲けの感覚は、往々にしてズレてくるもの。
・そのズレの原因は、会計上の損益と資金繰りの構造的な違いにある。
・減価償却費や借入金返済、消費税積立など、損益に反映されない数値を意識すべし。
・経営の血液とも言える現金の流れを強固にするため、正確な数字の把握を心がけたいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。







