2025年11月25日原価と費用を分ける【2つの意味】
今日もまだ親知らず抜歯後の痛みが続いています。
ただ、痛むことにもかなり慣れてきたため笑、とにかく気持ちを前向きに活動していきたいところです。
どうしてもこういった痛みについては、生活の中のいろんな部分に影響してきますので、
本当にQOLが下がってしまうものです。
とはいえ、気持ちは前向きに(!)本日の本題です。
原価と費用の復習
先日の記事の中で、原価と費用という2つの経費についてのお話をさせていただきました。
<2025年11月23日「サービスが終わっていても」経費とならない!?>
https://muratax.com/2025/11/23/9643/
前回の内容としては、売上高に直接的に紐づいているものは原価として捉えて、
それ以外の損失以外の経費については費用として、
その期間に対応するものを経費計上するということでした。
上述したように、原価については売上高と直接紐づくものであるため、
原価として処理すべき勘定科目を適切に原価として表示させて、
それ以外の項目については、販売費及び一般管理費や営業外費用として表示することによって、
適切な損益計算書が仕上がるというものです。
原価と費用を分けるメリット
また、この売上高に直接紐づかない経費については、基本的にそこまで大きな変動がないため、
この原価とそれ以外の経費の分類をすることにより、
毎月の損益の比較がしやすくなるということがあるんですね。
また、前期比較という面でも、この経費分類を整えておく必要があるというところ。
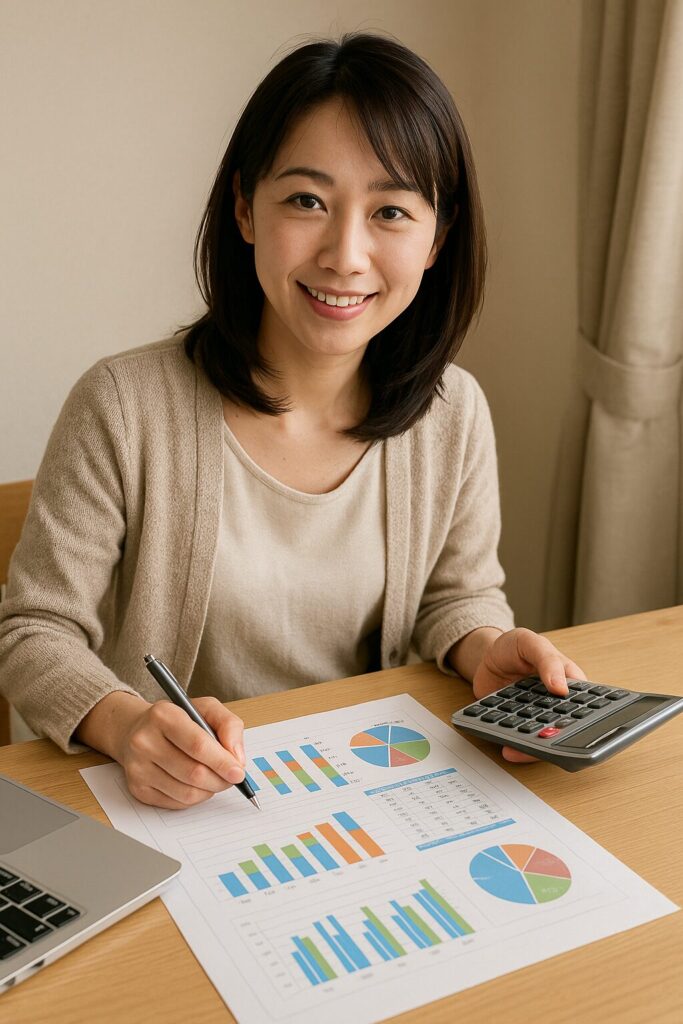
税務調査の視点で見た「勘定科目の怖さ」
そしてもう一点ここでのポイントがあります。
それは税務調査に対しての決算書の見せ方なんですね。
というのも、前期は原価として計上していた外注費を、
当期はその他の経費(法人で言えば販売費及び一般管理費や営業外費用)に表示しているとしたら、
結果の利益は変わらないとしても、
数字として原価と販管費の数字が大きく変わっていることになり、
そのことが原因で税務調査に選ばれてしまうということになりかねないわけです。
こういった勘定科目の適切な選択は、このような税務調査にまで派生してきますので、
そういった点も含めて、この経費の計上については注意をしたいところです。
「どの科目でもいい」は危険
税金を計算する上では、「経費は経費として計上すればどの科目でも良い」と言われがちなものですが、
実際の税務調査まで見据えると決してそうも言えないため、
そのようなことを念頭に置いて、経営分析の面でも税務調査の面でもマイナスにならないような会計処理をすることを心がけたいものです。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・原価とそれ以外の費用を適切な勘定科目で分類し、損益計算書に表示することにより、本来の経営の状況が見えるものである。
・こういった分類は、毎期継続することにより税務調査のリスクを下げられるものと心得ておくべし。
・勘定科目については、明確なルールを設けて、ある程度の継続性や統一性を持って会計処理を行うことを心がけたいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。







