2025年5月22日住民税と並んで「恐れるべき存在」とは
今日は古巣である北九州方面へ、
面談と元気な会合(のようなもの)へ。
今日は出先でパソコンが壊れるなど、
なかなか想定外の出来事が起こった
のですが、
なんとかパソコンなしでも過ごせたので、
一歩成長できたかなと思っています笑。
さて、かなり寝落ち気味の状態からの
本日の本題です。
==================
■先日の記事の中で
住民税の新年度についての
お話をさせていただきました。
<2025年4月10日「知っておきたい!」
住民税の正しい天引きについて>
https://muratax.com/2025/04/10/8854/
この住民税については、
6月から新年度が始まり、
前年の所得をベースに
税額が算定されます。
そんな中でもう一つ、
6月からスタートするものが。
それは『国民健康保険料』です。
■国民健康保険料は、厳密には税金では
ないのですが、
住民税と似た仕組みで、
6月からが新年度となります。
したがって、住民税と同じく、
6月に通知が届くわけですね。
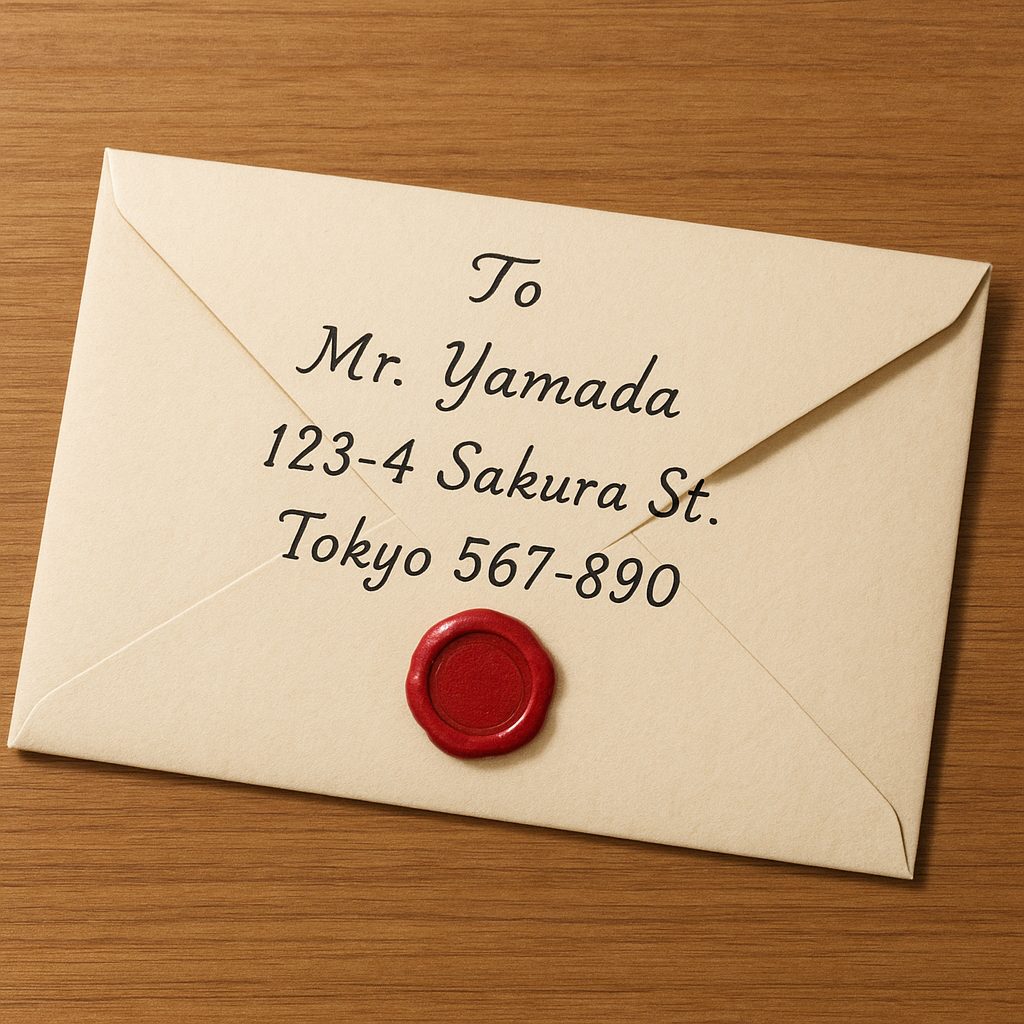
しかしこの保険料については、
計算方法が住民税と異なります。
■どう違うのかというと、
住民税は事業所得から
各種所得控除を差し引いた上で
税額が計算されるのに対して、
国保は【所得の合計】から
直接的に算出されます。
つまり扶養控除などの所得控除が
適用されないということ。
その結果、住民税に比べて
保険料が割高になりがちです。
■そのため、前年に所得が増えて
いると、国保が一気に上がる
ケースが想定されます。
このような状況を踏まえて、
対策を検討する必要があるわけです。
そこで一つの策となるのが
『マイクロ法人の活用』ですね。
■マイクロ法人については、
個人事業と並行して設立し、
最小限の利益を法人側で計上します。
そしてその利益と同額程度の役員報酬
を代表者個人にに支払うという形。
この役員報酬に対しては、
社会保険料(健康保険料と厚生年金)が
発生しますが、
ごく少額の報酬設定であれば、
社会保険料も少なくて済むのです。
■その結果、社会保険料全体が抑えられ、
国民健康保険料の負担よりも
トータルで有利になることが想定
されます。
とりわけ所得が高めの方にとっては、
負担が軽くなる可能性が高いです。
このような制度を活用すれば、
節税の本質である「手元により多くの
お金を残すこと」にも繋がることに。
■とはいえ、必ずしも全ての方にとって
得策とは限りません。
しかし、もし現在の国保が
相当な負担になっているなら、
マイクロ法人という選択肢も
一度検討してみる価値があります。
■ということで本日は、
住民税と並んで6月から始まる、
国民健康保険料についてお話して
まいりました。
前年の所得が高ければ、
それに応じて保険料も高くなります。
この保険料に対する対策として、
マイクロ法人の設立は
一つの選択肢となり得ます。
したがって、資金繰りや将来設計
を踏まえ、ご自身に合った方法を
模索しながら、
このマイクロ法人の設立も
視野に入れてみてはいかがでしょうか。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税と異なり、国保は基本的に総所得
のトータルに対してかかってくるもの。
・国保の増大に対しては、マイクロ法人
の設立も視野に入れておきたいところ。
・手元により多くのお金を残すという
節税の本質を常に見据え、
その時々の最善解を模索していきたい
ものである。
—
今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。







