2022年9月20日【「利子」「配当」「売却益」】・・個人事業で誤りなく処理していますか?
今日は事務所の新メンバーとの顔合わせ。
スタッフみんな個性的ではあるものの、
共通の理念の基に、同じ船に乗り、
それぞれ進んでいます。
またこれからがさらに楽しみですね。
さて、本題です。
---------------
■9月の半ばに差し掛かり、
個人事業主の方については
12月の年度末を前に
『税金面』の心配をされるように
なっているのではないか
と思います。
税理士が関与していれば
そこまで問題にならないのですが、
今日は、
【自ら確定申告をしている場合について
よくある誤り】
について、
お話ししていきたいと思います。
これは実際に、
自分で確定申告をしている方の
過去の申告書や会計帳簿を拝見する中で、
多い誤りでもありますので、
要注意な論点です。
今日はその注意すべき論点について
二つ見ていきます。
■まず、
【銀行預金の利子や配当金】
についての論点。
結論から言えば、
【たとえ事業用の通帳に入ってきた
事業のために使っているものからの
利息や配当金が入ったとしても、
確定申告上、事業所得には入れない】
ということなんですね。
どうしても通帳に入ってくるもの
ですので、
これを事業所得に加えてしまいがち
なのですが、
【利息と配当金については
事業所得ではない】
ということは肝に命じておきたい
ところです。
■では、
どのように処理をすれば
良いのでしょうか。
これについては収入があった時点で
【事業主借】
という勘定科目で処理をするのが
正解です。
どうしても『収入』ですので、
『売上』や『雑収入』として
処理をしてしまいがちなのですが、
そのような会計処理をしてしまうと、
その分収入が増えてしまうことになり、
余計な税を払ってしまう
ことになるので要注意です。
正確には『銀行預金の利子』については
【利子所得】
という分類がされ、
これについては、利息の受取時に
源泉徴収がされていて、
そこで課税関係は完結しているんですね。
■そして『配当金』については、
所得税の考え上、
【配当所得】
という所得区分に分類されますので、
これについても
【事業所得においては
考慮することは不要】
となります。
■二番目に注意したいこととして、
『事業で使用していた資産の売却益』
があります。
よくあるものとしては
【事業として使用していた車両の売却】。
実は、たとえ事業用に使用している車や
機械や備品であっても、
これを売却した際に
売却益が上がっているものについては、
【事業所得には入れない】
ということなんですね。
法人の会計などに
慣れている方については、
【固定資産売却益】
などとして収入に入れ込んで
しまいそうなものなのですが、
【個人ではそのルールが違う】
ということ。
正解としては、これも上述した
利子と同じように、
【事業主借】
として処理をすることになります。
■そして、
この事業用資産の売却については
【譲渡所得】
に分類されるんですね。
利子が『利子所得』、
配当が『配当所得』に分類されるように、
譲渡をした収入については
【譲渡所得】
になるということです。
これについても、
【事業所得に入れ込んで
収入が増えてしまう】
ということが懸念されるので、
その会計処理においては
十分な注意が必要である
と言えます。
特に『売却益』については、
場合によっては
大きな金額となるケースが
少なくありませんので、
やはりその取り扱いには
十分な注意が必要である
と言えます。
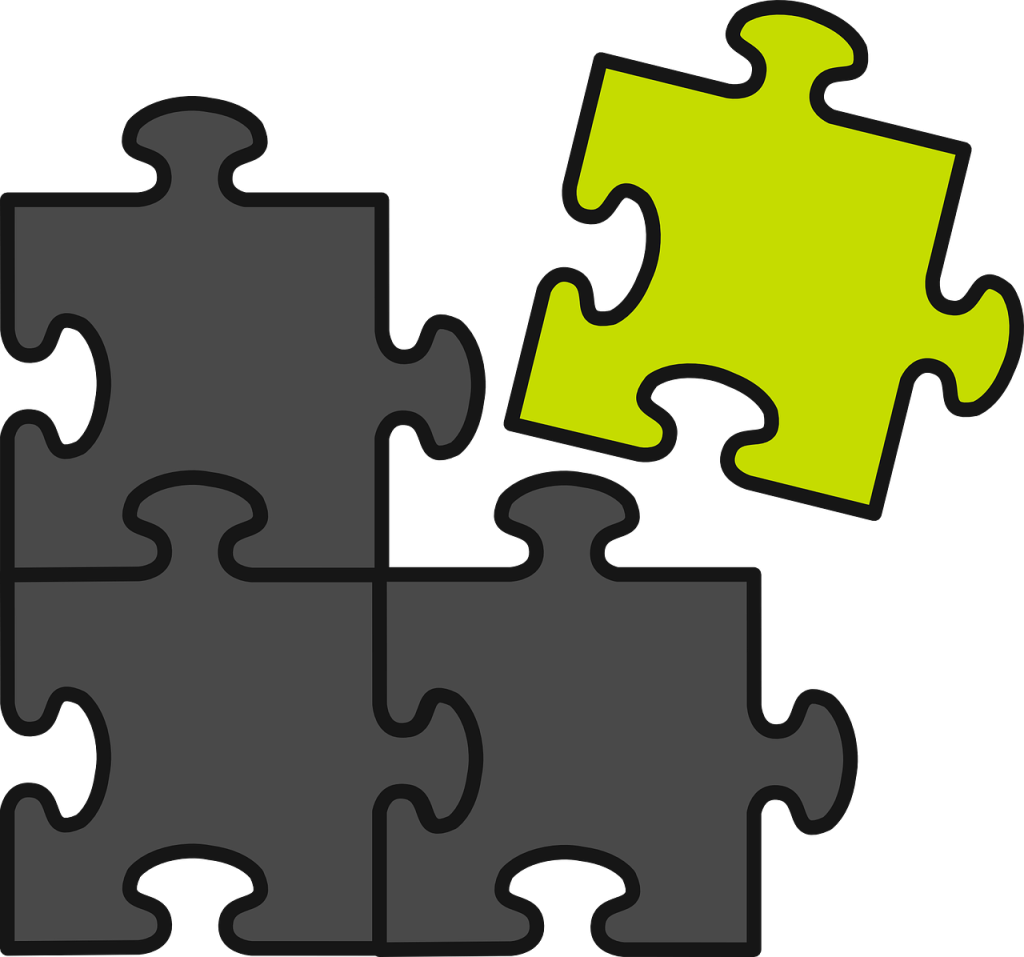 ■というわけで、
今日は個人事業主の誤りがちな
会計と税務の判断について、
主に利子や配当、そして
固定資産の売却について見てきました。
もしあなたが自分で
確定申告をされている際は、
この論点には十分注意をして
適正な会計処理と申告を心がけるように
しましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・『法人』と『個人』では
【その会計や税務の捉え方に
違いがあるもの】
と心得ておくべし。
・よく誤りがちなものとしては、
【利子や配当、そして固定資産の売却】
が考えられる。
・これらについては、
【事業所得とは無関係なもの】
と考え、それぞれ
【利子所得】【配当所得】【譲渡所得】
という分類がされるものと心得ておくべし。
・そして、
これらを収入に加えてしまうと、
【余計な税金を払うこと】
に繋がるため、
十分な注意が必要である
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■というわけで、
今日は個人事業主の誤りがちな
会計と税務の判断について、
主に利子や配当、そして
固定資産の売却について見てきました。
もしあなたが自分で
確定申告をされている際は、
この論点には十分注意をして
適正な会計処理と申告を心がけるように
しましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・『法人』と『個人』では
【その会計や税務の捉え方に
違いがあるもの】
と心得ておくべし。
・よく誤りがちなものとしては、
【利子や配当、そして固定資産の売却】
が考えられる。
・これらについては、
【事業所得とは無関係なもの】
と考え、それぞれ
【利子所得】【配当所得】【譲渡所得】
という分類がされるものと心得ておくべし。
・そして、
これらを収入に加えてしまうと、
【余計な税金を払うこと】
に繋がるため、
十分な注意が必要である
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。 






